現在、東京都内2つの美術館で、江戸時代後期の浮世絵師・歌川国芳(1798〜1861)の作品を中心にした二つの展覧会が開催されています。練馬区美術館の「国芳イズム−歌川国芳とその経脈」(4月10日まで)と、Bunkamura ザ・ミュージアムの「俺たちの国芳 わたしの国貞」(6月5日まで)です。国芳一門を描いたマンガ『ひらひら〜国芳一門浮世譚〜』(太田出版)と、若き日の国芳を描くマンガ『大江戸国芳よしづくし』(『週刊漫画ゴラク』連載中)の作者である崗田屋愉一(岡田屋鉄蔵)さんとともに展覧会を巡り、歌川国芳という絵師の魅力を探りました。
「おいらに描けねえもんは無いよ。この世のもんも、あの世のもんも、見たことのねえもんだってな」──武者絵から戯画まで驚異的な画域の幅広さ
──今日は2つの展覧会を巡って、100件を超える国芳作品を鑑賞することができました。練馬区美術館の展示作品は、コレクターであり浮世絵研究者の悳俊彦さんのコレクションで、国芳とその一門への愛がひしひしと伝わる作品群でした。また、Bunkamura ザ・ミュージアムの展示作品は、米国ボストン美術館の所蔵品で、保存状態が良くてびっくりしました。ひたすら国芳のパワーに圧倒された2展でした。
本当に楽しかったですね。国芳は、倶利伽羅紋紋(くりからもんもん)の水滸伝のヒーローを描いたかと思えば、壁の落書きに模して歌舞伎役者の似顔を描いてしまう。さらにはタヌキの玉袋みたいな戯画まで(笑)。これが一人の絵師の描いたものかと、その幅の広さに驚くばかりです。国芳の作品は「かっこいい!」とか「何だこれ!?」なんて、みんなでワイワイ言いながら見たくなりますね。美術館ではなかなか難しいですが......。江戸時代の人々も「こいつ、次は何をしでかしてくれるんだろう」と国芳の新作をワクワクしながら待っていたのではないでしょうか。
──当時「武者絵の国芳」と言われた国芳ですが、武者絵以外の画題も本当に幅広く描いていますよね。そのなかでも、彼のもう一つのお得意画題と言えば、やはり猫でしょうか。両展覧会とも、会場入り口で猫を使った造作やアニメーションを使用して、来館者を国芳ワールドへと誘っていました。崗田屋さんのマンガ『ひらひら〜国芳一門浮世譚〜』(以下『ひらひら』)と『大江戸国芳よしづくし』(以下『よしづくし』)の中でも、国芳の周りには常に猫が描かれていますね。
国芳は大の猫好きだったんです。私も猫を飼っているんですが、国芳の猫は、猫好きの人が描いた猫だということがすぐわかるんですよね。犬好きの人が描いた猫を見ると「あ、猫を抱っこしたことがないんだろうな」って思います。弟子の芳虎は、絵を見るかぎり犬派だろうな(笑)。本当に国芳は猫が好きで、猫好きが納得する猫を描いています。その細部まで行き届いた観察力はすごいと思います。
 (左)歌川国芳 六様性国芳自慢 先負 文覚上人 1860、(右)歌川国芳 流行猫の曲手まり 1841頃 ともに悳俊彦コレクション
(左)歌川国芳 六様性国芳自慢 先負 文覚上人 1860、(右)歌川国芳 流行猫の曲手まり 1841頃 ともに悳俊彦コレクション国芳は大迫力の躍動感あふれる浮世絵を描く一方で、こんなほのぼのした浮世絵も。左図は、滝壺の水流がマンガの効果線のような演出で描かれている。また、右図の猫は着物を着て二足歩行をしているが、仕草や表情に猫らしさがにじみ出る
──観察力といえば、崗田屋さんの『よしづくし』では、国芳が歌舞伎の舞台をスケッチするシーンがありますね。これは練馬区美術館で展示されている「国芳芝居草稿」から着想を得ているのでしょうか?
 歌川国芳 国芳芝居草稿(部分) 1818~44頃 悳俊彦コレクション
歌川国芳 国芳芝居草稿(部分) 1818~44頃 悳俊彦コレクションマンガ『よしづくし』では、パトロン・梅屋の計らいにより、国芳は人生初の桟敷席での歌舞伎鑑賞の機会を得る。興奮しながら舞台をスケッチする姿が団十郎の目に留まり、頼まれごとを引き受けたことから事件に巻き込まれることに。国芳は芝居小屋に通って、こうしたスケッチをいくつも描いていたのだろうか
はい、そうです。初めてこの作品を見たのは太田記念美術館(東京・原宿)での展示でした。国芳本人の直筆の線が見られて感動しました。役者の瞬間の動きを的確に写し取っていて、本当にうまいですよね。こうした国芳の下絵を、もっと見れたらと思います。浮世絵版画は、彫師や摺師の手を介したものなので、浮世絵師の息遣いが伝わってくるような下絵は貴重ですね。
残されている浮世絵師の版下絵を見ると、朱墨でラフを描いて、その上から黒い墨線で本番の線を描いてますよね。私がマンガを描くときの作業と一緒だなって。私もまずは青い線で下書きをして、それからペンを入れるので。大変参考になります。
「芳の字背負ってここに居る限り、めェらは皆仲間だ」──異色の浮世絵師集団、チーム国芳
──崗田屋さんが、国芳の作品で好きな作品はどの作品なんですか?
国芳の人となりがよくわかるという意味で大好きなのが《勇国芳桐対模様(いさましきくによしきりのついもよう)》ですね。国芳とその弟子たちの行列が描かれている作品です。一門の結束力が感じられて「チーム国芳」って感じですよね。この作品を見たとき、私もこの一門に入りたい、と思いました。

国芳一門の晴れやかな大行列。画面左で行列を率いている後ろ姿の人物が国芳本人だ。弟子たちは自分の名前を書いた扇子を手にしている。この作品は販売用でなく配り物だったらしい
──作品を見る限り、国芳自身を含めて、一門の中に厳格な序列は無いようですね。崗田屋さんのマンガのタイトル「ひらひら」というのも、弟子たちが国芳をそのように呼んでいたとか。
国芳が豊国一門にいたときに、二代豊国の襲名など、おそらく弟子同士の勢力争いみたいなものがあったと思うんです。国芳は性格的に、そういう上下関係やイザコザが嫌だったんじゃないかと。だから自分の名前は誰にも継がせなかったし、本人は「国芳の名を名乗ったら化けて出る」って言っていたらしいんです。他の作品では、遠景の提灯の一つひとつに弟子たちの名前を入れたりして。でも、自画像はいつも後ろ姿。そういうところがすごく好きです。
浮世絵師は売れてなんぼの世界ですから、当然、羽振りの良い人とそうでない人がいて、ちっとも仕事がもらえずに腐っていっちゃった人はいっぱいいたと思うんです。残された資料や逸話を見ていると、国芳一門は、いわゆる師弟関係や職業画家の集団というだけでない結びつきがあったように思います。気軽に誰でも弟子にしちゃっていたみたいですし、しょっちゅう破門にもしていたみたいですしね(笑)。
 『ひらひら~国芳一門浮世譚』より ©岡田屋鉄蔵(太田出版)
『ひらひら~国芳一門浮世譚』より ©岡田屋鉄蔵(太田出版)『ひらひら』の主人公・伝八郎は《勇国芳桐対模様》で「でん」という扇子を持つ人物がモデル。武家の出身で、父の仇討ちを果たした後、ある秘密を胸に入水するが、舟遊びをしていた国芳一門に救われる
──練馬区美術館の展覧会カタログ『国芳イズム』の解説によれば、芳宗なんて十数回も破門されてるみたいですね。『男はつらいよ』の寅さんのような......。
年の差を考えても、もはや親子喧嘩みたいなものだったんじゃないかと(笑)。みんな本当に国芳が好きで、「この親方を立てたい、この親方の力になりたい」という想いを持った連中が中心に集まっていたんだろうなって思うんです。
火消しに憧れて、火消し半纏を普段着にしていたとか、猫の供養を怠った一番弟子を破門にしたとか、残されているエピソードが、どれも大人気ないけれど、かわいい。きっと国芳には、人を惹きつけてやまない魅力と、誰もが放っておけなくなる、どうしようもなく人間としてダメなところがあったのではないでしょうか。生前も没後も、誰一人、国芳を悪く言う人がいなかった。愛すべき人物だったのだと思います。
弟子の河鍋暁斎(1831〜1889)が、のちに国芳画塾の様子を追想で描いていて、その絵がすごく楽しそうなんです。国芳は猫を抱きながら筆を走らせていて、すぐそばで兄弟子たちが相撲を取っていたりして。行儀の良い画塾ではなかったので、暁斎の親が心配して、彼は2年程度で狩野派に移されちゃうんですけれど。幼心に、よっぽど楽しかったんだと思います。

品川沖にクジラが現れたとの知らせを聞き、一門総出で見物に来た国芳たち。巨大なクジラに大はしゃぎ
「貧していても干されていても描く事を止めない、こんな絵師を捨て置けるものか」──パトロン・梅屋鶴寿に見出されるまで
──『よしづくし』は国芳のパトロンであった梅屋鶴寿の語りで物語が進行します。雨の日に偶然二人が出会うところから物語が始まりますね。二人が出会ったとき(文政5年頃)は、国芳はまだほとんど無名に近い浮世絵師でした。
『よしづくし』で描いた国芳と梅屋の出会いは、口伝にもとづいています。たまたま国芳の家の軒下で雨宿りをしていた梅屋に、国芳が絵を見せたというんですね。それで翌日、梅屋は2両の大金を持って国芳宅を再訪する。すべてのクリエイターにとって夢のような話ですが、後日談も含め、信憑性の高そうなエピソードなんです。現実はマンガよりも奇なり、なんですよ。
梅屋も若かったとはいえ、当時すでに文化人として目利きの力は十分備わっていたはずで、一瞬で国芳の絵に惚れ込んだということは、二人が出会ったとき、国芳はそれだけの画力を持っていたということになります。そこで『よしづくし』では、国芳が30歳を過ぎるまでなかなか才能を発揮できずにいた理由を、彼の画風が師の豊国風に矯正され、彼の持ち味が押し殺されていたから、という風に推測して描いています。

国芳一門の紅一点・芳玉から、国芳の若かりし頃の話を聞く伝八郎。国芳が「水滸伝」シリーズで一躍人気絵師の仲間入りを果たすのは31歳。当時としてはかなり遅咲きの浮世絵師だ
──現存する国芳の10〜20代の作品と、大ヒットを飛ばす「水滸伝」のシリーズとの間には、画力に大きな飛躍があります。『よしづくし』を読んで、崗田屋さんの推測は非常に説得力があると思いました。特に駆け出しの絵師においては、描いたものがそのまますんなり世に出ることはありません。
国芳本人は、本当に不器用な性格だったんだと思うんです。セルフプロデュース能力が皆無だったんではないかと(笑)。豊国も彼の筆に光るものを感じながら、それを引き出せずにいた。国芳は経済的に困窮していて、画塾の費用がまともに払えていなかったという話もありますが。国芳の能力を開花させるために、さまざまな根回しをしたプロデューサー、それが梅屋だというのが私の推論です。
──浮世絵は出版物ですから、消費者のニーズがあり、クライアントの要望があり、制作コストの計算が合わなければならない。若い頃の血気盛んな国芳には、そのあたりの折り合いをつける能力、要は仕事におけるコミュニケーション能力が足りなかったのかもしれませんね。
うぅ、耳が痛い(笑)。はい、それはあると思うんです。つまり、仕事上で自分のやりたいことを実現するには、ある程度、相手を説得して納得させなければいけない。それが多分、若い頃の国芳は上手くできなくて、ほとんど仕事がもらえなかった。そこを梅屋がうまく立ち回ってくれるようになったのではないかと。
「水滸伝」のシリーズの仕掛け人も、私は梅屋だったと思っています。彼は商人ですから、流行はつくるものだということがわかっていた。おそらく時流を察知して、最高のタイミングで国芳の武者絵を世に送り出したんです。梅屋と出会わなければ国芳は歴史に埋もれていたと思っています。
──国芳の作品から、どんどん想像が膨らんでいきますね。本当に国芳は興味深い浮世絵師です。後編では、さらに国芳像を探っていきたいと思います。
PROFILE
おかだや・ゆいち 2007年『タンゴの男』(宙出版)でデビュー。2010年奇譚時代劇『千』(白泉社)発表後、時代劇ジャンルに活動の場を広げる。2011年、国芳一門を題材にした『ひらひら国芳一門浮世譚』(太田出版)を発表、文化庁メディア芸術祭推薦作品に選出される。現在、少年画報社ヤングキングアワーズ誌にて『無尽~MUJIN』連載中。『大江戸国芳よしづくし』の続編は今秋『週刊漫画ゴラク』に連載予定。主な作品に『極楽長屋』(MagGarden社)、『口入屋兇次』(集英社)など。ローマ日本文化会館で開催中(4月7日まで)の「マンガ・北斎・漫画―現代日本マンガから見た『北斎漫画』」展に出品。公式サイトURL:http://okdy.sakura.ne.jp
会場:練馬区立美術館
住所:東京都練馬区貫井1-36-16
電話番号:03-3577-1821
開館時間:10:00〜18:00(入館は閉館30分前まで)
休館日:月休
入館料:一般 800円 / 大高生、65~74歳 600円 / 中学生以下および75歳以上(要証明証) 無料
URL:http://www.neribun.or.jp/museum/
会場:Bunkamura ザ・ミュージアム
住所:東京都渋谷区道玄坂2-24-1
電話番号:03-5777-8600(ハローダイヤル)
開館時間:10:00~19:00 ※ 毎週金・土曜日は21:00まで(入館は閉館の30分前まで)
入館料:一般 1500円 / 大高生 1000円 / 中学生 700円
URL:http://www.ntv.co.jp/kunikuni/


























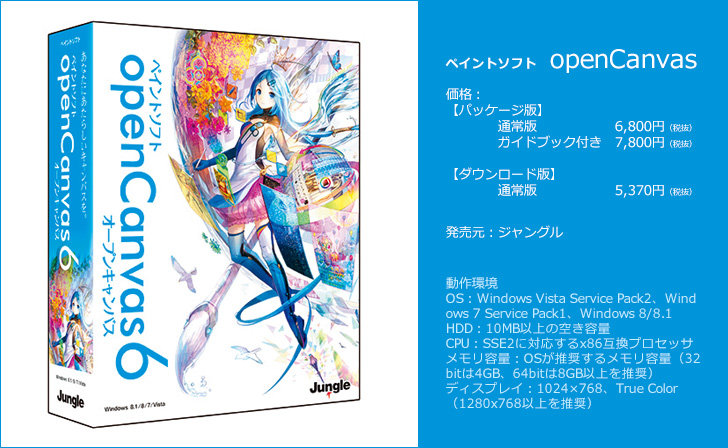








 北浦和、氷川神社へ向かう道 撮影=ミヤギフトシ
北浦和、氷川神社へ向かう道 撮影=ミヤギフトシ






